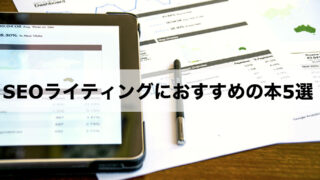Warning: Undefined array key 6 in /home/frwill/webtasu.com/public_html/wp-content/plugins/webtasu-writing/webtasu-writing.php on line 2121
4Pは知ってるんだけど、3Cってなに?この2つは何か関係があるの?
今回は、マーケティングの用語として使われる「4P」と「3C」について紹介していきます。先に言っておきますが、ここで紹介する3Cは、4C(Consumer・Cost・Convenience・Communication)とは全くの別物です。
初めて「3C」という言葉を聞いた人もいることでしょう。
この記事では、4Pと3Cの関係性や、3Cの要素は何かということを、初心者でもわかるように事例を挙げながら紹介していきます。
マーケティングで用いられる4Pと3Cの関係性

マーケティングで用いられる4Pと3Cには一体どんな関係性があるのでしょうか。
まず、4Pと言うのは、
- Place
- Price
- Product
- Promotion
の4つの頭文字を取ったマーケティングの言葉で、企業目線で製品やサービスの分析をするときに用います。
詳しい4Pの内容に関してはこちら↓

一方で3Cと言うのは、
- Customer
- Company
- Competitor
の3つの頭文字を取ったマーケティングの言葉で、自社の分析をするときに用います。
4Pと3Cを用いることで、自社の分析と取り扱っている製品やサービスの分析を行えるため、より具体的にマーケティング施策を考えることができます。
この2つのマーケティングのフレームワークを使うときには、先に「3C」から行うことを頭に入れておいてください。
マーケティングの「3C」で何を分析するのか

マーケティングの「3C」の分析は、経営資源・戦略・業績の事実を整理するための考え方なので、現状の分析から実際のアクションに繋げることを目的としています。
ですから、分析後マーケティングにすぐに活かせるフレームワークの1つと言えます。分析をした内容は、マーケティングに用いなければ意味がないので、すぐに実践に落とし込めるように本気で分析に取り組んでください。
- Customer(顧客・市場)
- Company(自社)
- Competitor(競合)
それでは次の章から、各要素について紹介していきます。
Customer(顧客・市場)
1つ目のCは顧客や市場を表す「Customer」です。
顧客や市場の調査を意味します。どういうことかと言うと、顧客のことや市場について知らないままだと、顧客が求めているものや市場が求めているものを把握することができず、自社の強みや弱みがわからないままになってしまうからです。
ここでは、
- 顧客が求めているもの、求めていないもの
- 市場が求めているもの、求めていないもの
- 市場の将来性はどうなっていくのか
- 顧客や市場の特徴
を把握します。
Company(自社)
2つ目のCは自社を指す「Company」です。
自社の分析を意味します。先ほどの「Customer」で出てきた顧客や市場の状況を加味して、自社の強みや弱みを探ります。
この際、自社の現在の売上高や市場シェア、人材を考慮し、できるだけ現実的な自社の強みや弱みの分析を行いましょう。
Competitor(競合)
3つ目のCは競合を意味する「Competiter」です。
競合他社がどんな戦略をしているか分析することを意味します。競合の売り上げや市場シェアなどを加味し、なぜ競合他社の方が優っているのか、なぜ自社が優っているのかを分析します。
競合が一体どのようにして売り上げを立て、市場シェアを拡大していったのか、売り上げ・市場シェアの拡大はどんなことが理由なのかを分析しましょう。
4Pと3Cを組み合わせたマーケティングをすると

4Pと3Cを組み合わせたマーケティングを行うとどうなるのでしょうか。
3Cで自社の強みや競合について分析したものを、4Pと掛け合わせて使うことで、どの方向を目指してマーケティング戦略を考えればいいかがはっきりとしてきます。
ただ4Pだけを使って自社製品・サービスの分析をするだけではなく、3Cで分析した要素を掛け合わせることで、より正確なマーケティング戦略を考えることができるのです。
3Cの後に4Pを使って自社製品の分析をする場合には、競合他社の製品も一緒に考えてみると、その後に取るべきマーケティング戦略が考えやすくなります。
- 3C分析をする。
- 3C分析のときに比較した競合の4Pを調べる。
- 自社と競合の4P分析をして比べる。
- 4Pの4つの要素を、自社と競合を比べて優劣をつける。
- 自社が競合に優れているところをさらに伸ばすのか、劣っているところを改善するのか決める。
この流れで分析を行いましょう。
3Cと4Pを組み合わせてマーケティング戦略を立ててみた

ここからは、実際に3Cと4Pを組み合わせてマーケティング戦略を立ててみた結果を紹介していきます。今回は「Nintendo Switch」を事例として用いることにします。

※これは僕の独断と偏見です。実際に企業がこの通りにマーケティング戦略を立てているとは限りません。この記事を書きながら即興で考えた具体例です。
3C分析
まずは3C分析をしていきます。
- Customer:テレビゲームの本体に対しての市場は飽和しつつある。テレビゲームは家でやることが当たり前で持ち運びができず、移動中や旅先でゲームをすることができずに歯がゆ思いをしている顧客が一定数いる。「テレビがなくてもできるテレビゲーム」が今後出てくるかもしれない。
- Conpany:テレビゲームの市場シェアは任天堂が国内トップ。テレビゲームの本体の売り方やプロモーションに関してはノウハウがある。ゲーム本体によって売れる売れないを経験してきているから、売れなかった時の事前の対策をバッチリ取ることができる。
- Conpetitor:「PlayStation」を開発したSONYが競合。SONYはプレステシリーズをアップデートして販売を続けているが、売り上げは落ちていない。プロモーションや移行のさせ方が上手。大人向けのゲームソフトが多い印象。
このように考えられました。
競合との4P分析
今分析した3C分析を元に、4P分析を行なっていきましょう。
- Place:ゲーム機本体の種類も多く、ゲームソフトごとに対応しているゲーム機本体が異なるため、1つの店舗にいくつもの任天堂製のゲームを置いてもらえる。
- Price:Nintendo Switchはおよそ¥30,000。
- Product:いつでもどこでも持ち運びができて、1つのゲームで3種類の遊び方ができる。
- Promotion:製品発売前からのプレスリリースやローンチ。販売後は本体のCMやゲームソフトのCMを流し、認知度の向上に務めている。
- Place:ゲーム機本体の種類が少なく昔の型のプレステを取り扱うところは少ないため、SONY製のゲームを置いてくれる数は多くない。
- Price:PS4だとおよそ¥30,000前後で購入できる。
- Product:プレステシリーズはアップデートされて発売される。操作方法が過去のプレステとほとんど変わらないため、顧客はすぐに新しいプレステ本体に馴染むことができる。大人向けのゲームソフトが多い。DVDも観られる。
- Promotion:CMはほとんど打たない。広告費は全くかけていないが、熱狂的なプレステユーザーのSNSによる口コミや、人気シリーズ作品が新しいプレステに対応してくるため、新しいプレステを買うしかない。
優劣をつける
そして、任天堂と競合のSONYの分析ができたところで、4Pの各要素に優劣をつけていきます。
- Place:任天堂
- Price:—–
- Product:SONY
- Promotion: SONY
※優れている会社名を右横に記載しています。「——」は優劣がつけられない部分です。
こうしてみると、任天堂は1つの部分でしか優れていないということがわかりました。
優劣のどちらを基準にするか決める
優劣を付けることができたら、今度は
- 優れているところを伸ばすのか
- 劣っているところを改善するのか
を決め、マーケティング戦略のゴールを設定します。
例えば「劣っている部分」を基準にして考えるならば、任天堂はマーケティング戦略のゴールを
- 大人向けのゲームソフトを1年以内に開発する。
- DVDを観られたりYoutubeと連携させられる機能を持つゲーム機を1年以内に開発する。
- 半年後、売り上げを現状維持した状態で広告費を現状から1/3カット。
などのように、設定しましょう。
このようにして3Cと4Pを使って考えることで、「SONYが新製品を出したから対抗するために新製品を出そう」や「広告費をもっと使って認知度を高めよう」のような、目先の動きに惑わされることなく、長期的に考えられた戦略を立てることが可能になります。
本来の強みを活かし、本来の弱みを改善する戦略が立てられるため、理にかなっています。
まとめ
今回の記事で、3Cと4Pを掛け合わせて行うマーケティングフレームワークが、いかに具体的な戦略を立てられるかわかっていただけたはずです。
ただ4Pだけで考えるよりも、3Cだけで考えるよりも、両者を融合させることが効果的です。いきなり4Pと3Cを使うことは難しいと思いますから、僕が任天堂のマーケティング戦略を考えるように、具体例を挙げながら4Pと3Cについて考えてみると、より知識が深まります。
自分の中で「使いこなせる自信がある!」と思えるまで勉強・テストをして、実際に会社のマーケティングに活かしてみてください。